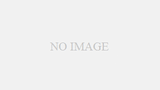長崎御朱印巡りで、長崎県大村市に鎮座する大村神社(おおむらじんじゃ)にお詣りをして御朱印を拝受して来ました。藤原純友公及びその一族を「御霊宮大明神」と称して領内西大村池田山に創祀した神社さんです。今日で、716社目です。
一の鳥居
長崎御朱印巡り 第2弾、次に向かったのは 大村神社さんです。桜が見ごろで たくさんの人が居ました。
二の鳥居
二の鳥居です。
手水舎
手水舎です。
拝殿
拝殿です。
由緒
文化2年(1805年)に時の大村藩主大村純昌が祖先とする藤原純友公及びその一族を「御霊宮大明神(ごりょうぐう — )」と称して領内西大村池田山に創祀した神社を起源とし、文化11年には純鎮公を、天保9年(1838年)には純昌も「純昌公」として合祀された。その後藩主から年間祭祀料を支弁される等の崇敬を受け、明治3年(1870年)には更に純鎮、純昌以外の歴代藩主9代を合祀して社名を「常磐神社」と改称した。
明治4年に廃藩置県となると、旧藩主と領民との関係が希薄化することを危惧した大村城下の旧藩士が発起人となって旧領民が一体となって祀る神社とされ、同7年に村社に列したが、池田山は参拝に不便であるとされたため、荒れ地と化していた玖島城本丸跡を新社地とする事に決し、明治16年に社地と社名の変更を国に願い出て同年11月に社殿造営に着工、翌17年5月に遷座して鎮座地名に因る現社名へ改称、翌18年に最後の藩主であった純熈を「純熈公」として合祀、同年2月19日に県社に昇格した。なお、新社殿竣工までは池田山から三城町の富松神社[1]へ仮遷座されていた。また、「大村神社」として発足した当初は勤王の志が篤いとの事から純熈公を含む現主祭神7柱の霊璽のみを本殿に祀り、他の祭神は本殿左に別殿を設けて祀っていたが、大正4年(1915年)に全て本殿に合祀された。
戦後の昭和30年(1955年)には社殿地を大村家から寄進されている。
社務所
御朱印は こちらの社務所でいただけます。
御守
御守です。
御朱印
御朱印です。直書きでお受けしました。ありがとうございました。
御朱印帳
御朱印帳も いくつかの種類がありました。
オリジナル御朱印帳
オリジナル御朱印帳もありました。
箔押し朱印
箔押しの御朱印もありました。迷いましたが 今回は通常の御朱印のみ お受けしました。
貝吹石
貝吹石(通称:ほら石)
円形の野石であって、上に大小二つの穴があり、小さな方を吹くと法螺貝(ほらがい)の音を出すので此の名がある。萱瀬村から寄附されたもので昔天正年間竜造寺隆信が萱瀬村を襲撃の時、同村の郷士等が藩主純忠の命を奉じて管無田の砦に立籠り隆信と戦うとき此石の穴を吹いて合図の陣具に代用し終に敵を追い退けたと云う伝説がある。
看板より
駐車場
一の鳥居の近くに駐車場はあります。グー〇ルのナビで行くと 案内してもらえます。
神社情報
大村神社(おおむらじんじゃ)
長崎県大村市玖島1丁目34
御祭神:大村直澄公 外6柱
例祭日: 4月8日
正確に言うと神社だけで1000社です
今日で 716社目の
御朱印をいただきました。
残り 284社です。
長崎の御朱印が拝受できる神社
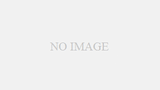
長崎の御朱印が拝受できる寺社
長崎ご当地グルメ